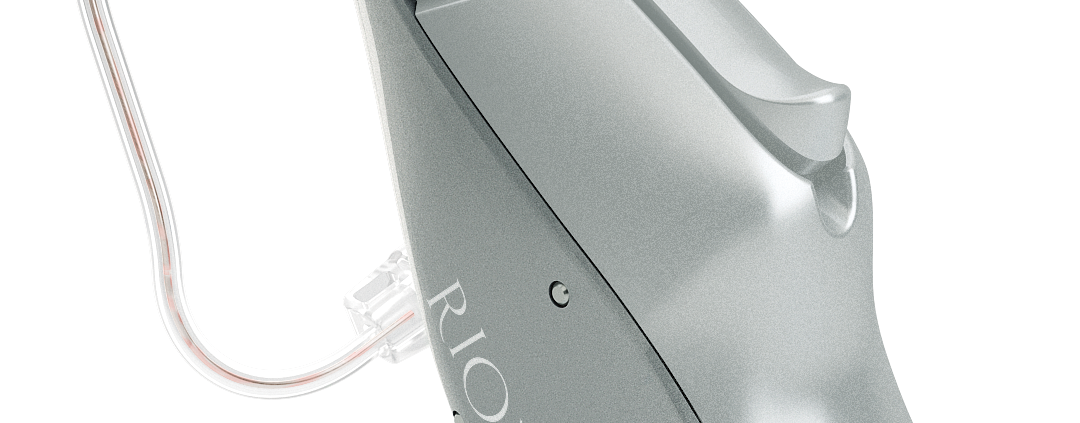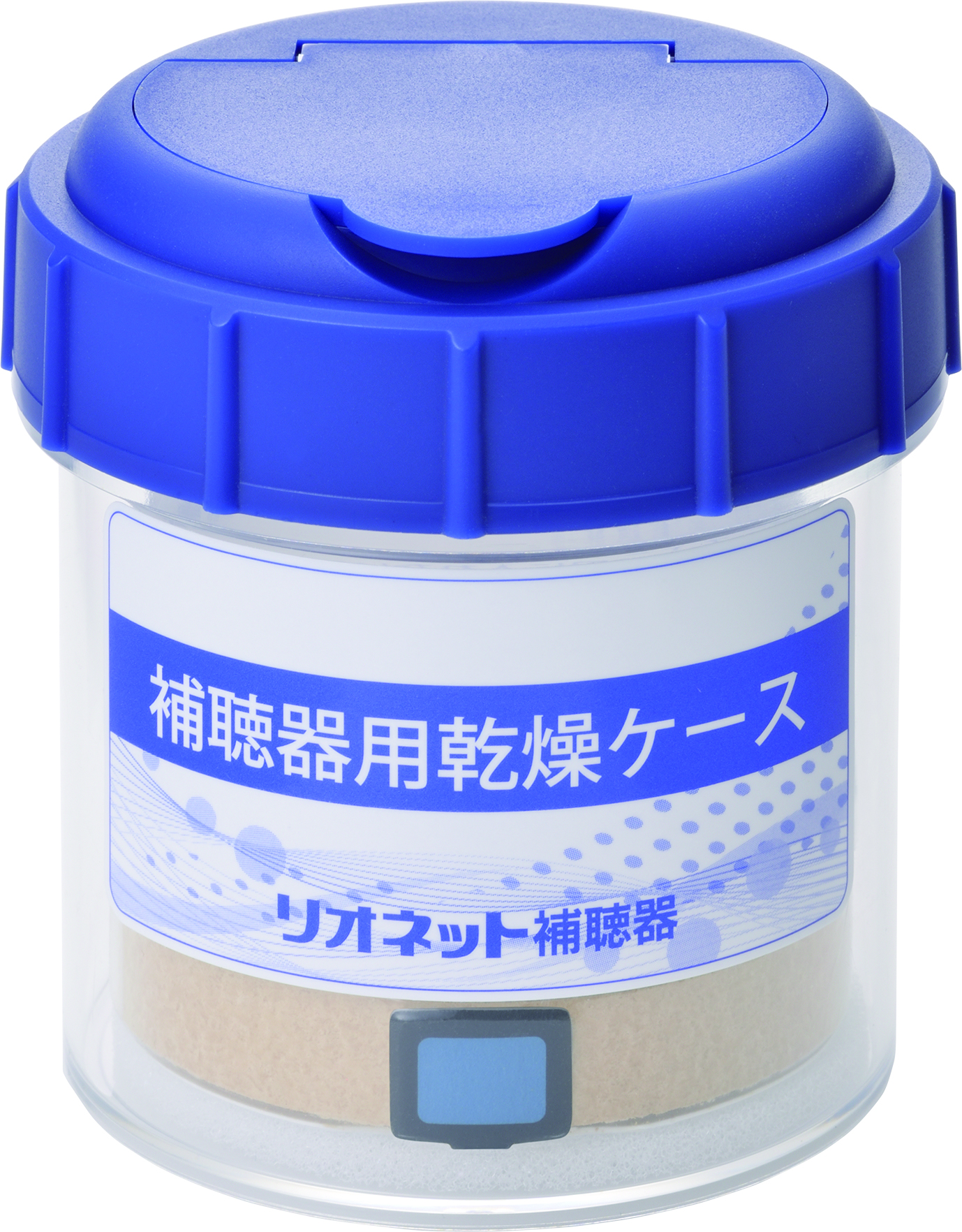補聴器の助成制度について徹底解説![23区]
補聴器を調べると、最初に驚かれるのは価格だと思います。
近年、自治体では、補聴器の購入費を助成しようという動きが活発です。
今回は東京都23区の助成制度をご紹介いたします。
※下記の地域にお住まいの方は、別ページにてご案内いたします。
なお、聴覚障害による手帳をお持ちの方は、助成制度がご利用いただけません。
手帳をお持ちの方は、市区町村の福祉課にて申請手続きする事で、補聴器の費用が支給される制度が別にございます。そちらをご利用ください。
【目次】(4月から制度内容が変わるところがあります)
- 足立区
- 荒川区
- 板橋区
- 江戸川区
- 大田区
- 葛飾区(7月から変わります)
- 北区
- 江東区
- 品川区
- 渋谷区
- 新宿区
- 杉並区
- 墨田区
- 世田谷区
- 台東区
- 中央区
- 千代田区
- 豊島区
- 中野区
- 練馬区
- 文京区
- 港区
- 目黒区
- まとめ
足立区
[助成額] 上限50,000円(購入金額が助成金額未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●区内に住所を有する満65歳以上の方
●耳鼻科の医師から意見書が得られる方
●両耳の聴力レベルが40㏈以上70㏈未満の方、または片耳が40㏈以上90㏈未満且つもう片耳が40㏈以上50㏈未満の方
[申請窓口] 地域包括ケア推進課、各地域包括支援センター、足立福祉事務所各課
詳しくはこちらをクリックしてください(足立区ホームページへ移動します)
荒川区
[助成額] 上限72,450円(購入金額が助成金額未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●区内に住所を有する満65歳以上の方
●耳鼻科の医師が補聴器の必要性を認めた方
原則として両耳の聴力レベル40㏈以上70㏈未満の方
[申請窓口] 高齢者福祉課高齢者福祉係(本庁舎2階)
詳しくはこちらをクリックしてください(荒川区ホームページへ移動します)
板橋区
[助成額] 上限50,000円(購入金額が助成金額未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●区内に住所を有する65歳以上の方
●住民税非課税世帯の方
●耳鼻科の医師が補聴器の必要性を認め、両耳または片耳が中等度以上の難聴者
[申請窓口] 長寿社会推進課高齢者相談係(北館2階)、おとしより保健福祉センター、おとしより相談センター
詳しくはこちらをクリックしてください(板橋区ホームページへ移動します)
江戸川区
[助成額] 上限35,000円(購入金額が助成金額未満の場合は、購入金額となる 郵送可)
[対象者]
●江戸川区民の満65歳以上の方
●住民税非課税の方
●過去にこの制度による助成を受けていない方
●耳鼻科の医師が所定の基準を満たすと認められ、証明とオージオグラムを提出できる方
※所定の基準とは、両耳の聴力レベルが40㏈以上70㏈未満または、聴力レベルが40㏈未満の場合でも耳鼻科の医師が補聴器の必要性があると判断した場合(4分法)
[申請窓口] 福祉推進課孝行係(区役所南棟2階)、健康サポートセンター、熟年相談室(地域包括支援センター)
※申請前に耳鼻咽喉科を受診してください
詳しくはこちらをクリックしてください(江戸川区ホームページへ移動します)
大田区
[助成額] 上限35,000円(購入金額が助成金額未満の場合は、購入金額となる)
●満65歳以上の方で、区内に住所を有し、現に居住していること
●住民税非課税世帯
●耳鼻科の医師が所定の基準を満たすと認められ、意見書を得られる方
※所定の基準とは、両耳の聴力レベルが40㏈以上70㏈未満の中程度難聴(4分法)
[申請窓口] 管轄の地域包括支援センター
詳しくはこちらをクリックしてください(大田区ホームページへ移動します)
葛飾区(7月から変わります)
[助成額] 上限144,900円(住民税課税者は上限72,450円)
[対象者]
●葛飾区民の満65歳以上の方
●医師が補聴器の必要性を認める方
[申請窓口] 高齢者支援課(区役所2階 郵送可)
詳しくはこちらをクリックしてください(葛飾区ホームページへ移動します)
北区
[助成額] 上限70,000円(購入金額が助成金未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●区内に居住し、住民登録がある満65歳以上の方
●住民税非課税の方
●耳鼻科の医師が補聴器の使用が望ましいと判定した中等度難聴者
両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満
●過去にこの事業の助成を受けていない方、助成決定から5年経過してる方
[申請窓口] 高齢福祉課
詳しくはこちらをクリックしてください(北区ホームページへ移動します)
江東区
[助成内容] 現物支給(耳かけ型か箱型)または、上限72,450円(どちらか1つのみ 郵送可)
[対象者]
●区内在住の65歳以上の方
●区で定める所得以下の方
●前回の支給決定から5年経過していること(再申請の場合)
[申請窓口] 介護保険課在宅支援係(区役所3階)、長寿サポートセンター
詳しくはこちらをクリックしてください(江東区役所ホームページへ移動します)
品川区
[助成額] 上限72,450円(購入金額が助成金額未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●区内に住所を有する満65歳以上の方
●耳鼻科の医師が所定の基準を満たす証明を受けた方
1.両耳が40デシベル以上70デシベル未満(中等度難聴)と診断された方
2.その他、助成対象者として補聴器装用の必要性が認められた方
[申請窓口] 高齢者地域支援課
詳しくはこちらをクリックしてください(品川区ホームページへ移動します)
渋谷区
[助成額] 上限45,000円(購入金額が助成金額未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●区内在住の65歳以上の方
●住民税非課税の方
●耳鼻科の医師が所定の基準を満たす証明を受けた方
所定の基準とは、両耳の聴力レベルが40㏈以上70㏈未満または、左右いずれかの聴力レベルが40㏈未満で医師が補聴器の必要性を認めた方
[申請窓口] 高齢者福祉課サービス事業係(区役所5階)、地域包括支援センター
詳しくはこちらをクリックしてください(渋谷区ホームページへ移動します)
新宿区
[助成内容] 現物支給(耳かけ型か箱型)または、上限33,000円(どちらか1つのみ 郵送可)
[対象者]
●70歳以上で聴力が低下した方
●前回支給日から5年間以内の方
[申請窓口] 高齢者支援課(区役所2階)、各高齢者総合相談センター
詳しくはこちらをクリックしてください(新宿区ホームページへ移動します)
杉並区
[助成額] 上限48,300円(住民税課税世帯は上限24,200円)
[対象者]
●区内に住所を有する65歳以上の方
●補聴器相談医または、杉並区内補聴器相談医名簿の医師から補聴器の必要性を認められた方
[申請窓口] 地域包括センター、高齢者在宅支援課
詳しくはこちらをクリックしてください(杉並区ホームページへ移動します)
墨田区
[助成額] 上限35,000円(住民税課税世帯は上限20,000円)
[対象者]
●区内に住所を有する、満65歳以上の方
●耳鼻科の医師から所定の基準を満たすと認められ、意見書を提出できる方
※所定の基準とは、両耳の聴力レベルが50㏈以上または、一測耳の聴力レベル30㏈以上かつ、他耳の聴力レベルが70㏈以上(三分法)
[申請窓口] 高齢者福祉課支援係(区役所4階)、高齢者支援総合センター
詳しくはこちらをクリックしてください(墨田区役所ホームページへ移動します)
世田谷区
※年齢・学生によって内容が一部異なります。詳細は世田谷区ホームページでご確認ください。
[助成額] (65歳以上)上限50,000円(購入金額が助成金未満の場合は、購入金額となる)
(18歳~64歳)上限50,000円(両耳の場合100,000円)
(学生の場合)上限137,000円(両耳の場合274,000円)
[対象者]
●区内在住者
●住民税非課税者(65歳以上)/住民税非課税世帯(18歳~64歳)
●耳鼻科の医師が補聴器の必要性を認めた方
聴力レベルが40デシベル以上の方(学生は概ね30㏈以上)
●過去5年以内に助成を受けたのとのない方
[申請窓口] 高齢福祉課
詳しくは下記をクリックしてください(世田谷区ホームページへ移動します)
18歳~64歳の方
65歳以上の方
台東区
[助成額] 上限144,900円(住民税課税者は上限72,450円)
[対象者]
●台東区に住所を有する65歳以上の方
●耳鼻咽喉科医によって補聴器の装用が必要と認められた方
●聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちでない方
●過去にこの事業の助成を受けていない方
[申請窓口] 高齢福祉課(区役所2階⑤番窓口)
詳しくはこちらをクリックしてください(台東区ホームページへ移動します)
中央区
[助成額] 上限35,000円(購入金額が助成金額未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●65歳以上の区内在住者
●耳鼻科の医師が補聴器の必要性を認める方
●区で定める所得以下の方
●過去にこの助成を受けていないこと
[申請窓口] 高齢者福祉課(区役所4階)
詳しくはこちらをクリックしてください(中央区ホームページへ移動します)
千代田区
[助成額] 補聴器購入費の9割助成(上限50,000円 購入金額が助成金額未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●千代田区内に住所を有し、現に居住していること
●補聴器の必要性を認める医師の意見書を得る事ができる方
●片耳の聴力レベルが40㏈以上の方
●区で定める所得範囲内の方
●過去にこの助成を受けていないこと。または、助成決定日から5年以上経過している。
[申請窓口] 障害福祉課(区役所3階)
詳しくはこちらをクリックしてください(千代田区ホームページへ移動します)
豊島区
[助成額] 上限50,000円(住民税課税の人は上限20,000円 購入金額が助成金未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●区内に住所を有する65歳以上の方
●耳鼻科の医師から中程度難聴程度と証明を受けた方
[申請窓口] 高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)
詳しくはこちらをクリックしてください(豊島区ホームページへ移動します)
中野区
[助成額] 1台につき上限45,000円 両耳(2台分)の場合上限90,000円(購入金額が助成金未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●区の住民基本台帳に登録されている65歳以上の方
●世帯の生計中心者の前年の合計所得金額が350万円未満の方
●中等度難聴と診断された方又は耳鼻咽喉科の医師から装用が必要と認められた方
●過去にこの事業の助成を受けていない方
[申請窓口] 地域包括ケア課
詳しくはこちらをクリックしてください(中野区ホームページへ移動します)
練馬区
[助成額] 上限72,000円(住民税課税の人は上限36,000円 購入金額が助成金未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●区内に住所を有する65歳以上の方
●耳鼻科の医師から意見書を得られる方(両耳の聴力レベル40㏈以上70㏈未満)
●過去5年以内に補聴器購入費用の助成を受けていない方
[申請窓口] 高齢者支援課高齢給付係(区役所西庁舎3階 郵送可)、地域包括支援センター
詳しくはこちらをクリックしてください(練馬区ホームページへ移動します)
文京区
[助成額] 上限72,450円(購入金額が助成金額未満の場合は、購入金額となる 郵送可)
[対象者]
●区内に住所を有する65歳以上の方
●医師が補聴器の必要性を認める方
●過去5年以内に本助成金の交付を受けていない方
[申請窓口] 高齢福祉課(文京シビックセンター9階南側)
詳しくはこちらをクリックしてください(文京区ホームページへ移動します)
港区
[助成額] 上限144,900円(住民税課税の人は上限72,450円 購入金額が助成金未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●区内に住所がある60歳以上の方
●区で指定する医療機関(補聴器相談医在籍)の医師が補聴器を必要と認めた方
[申請窓口] 総合支所区民課保健福祉係、高齢者相談センター
詳しくはこちらをクリックしてください(港区ホームページへ移動します)
目黒区
[助成額] 上限50,000円(購入金額が助成金未満の場合は、購入金額となる)
[対象者]
●区内在住者の満65歳以上の方
●住民税非課税の方
●耳鼻科の医師が所定の基準を満たす証明を受けた方
1.両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満のかた
2.助成対象者として補聴器装用の必要性を認められたかた
[申請窓口] 高齢福祉課
詳しくはこちらをクリックしてください(目黒区ホームページへ移動します)
まとめ
東京都23区すべてで助成制度が実施されています。
自治体によって内容が異なりますので、ぜひお住いの地域の助成制度をご確認ください。
タスク補聴器では、お住まい地域での助成制度、手続きの流れををご説明いたします。
その他にも、医療費控除のご案内など、補聴器を通して受けられる補助についてご説明いたしております。
助成制度や補助について知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
ホームページからもお問い合わせができます。
お問合せフォーム